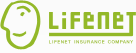みなさん、こんにちは。営業本部の吉見です。
まずは、「真珠の耳飾りの少女」から。
ヨハネス・フェルメールは1632年生まれのオランダの画家。「真珠の耳飾りの少女」はフェルメールの代表作のひとつです。
※フェルメール作品はこちらから。
※THE HUFFINGTON POSTさんの記事で、フェルメール作品をスライドショーで観賞できます。
フェルメールの作品は30数点しか現存しない【画像集】
![]() (出典:ザ・ハフィントン・ポスト・ジャパン株式会社)
(出典:ザ・ハフィントン・ポスト・ジャパン株式会社)
かなり有名な絵ですので、ご存知の方も多いかと思います。
とはいえ、名画を語るというガラでもないので、ここは、敬愛してやまない福岡ハカセ(福岡伸一さん)の言葉をお借りしたいと思います。
※以下、『』内は、福岡伸一さんの著書『フェルメール 光の王国』より引用。
福岡ハカセはフェルメールの絵に「微分的な要素」を見出します。
『 ≪微分≫というのは、動いているもの、移ろいゆくものを、その一瞬だけ、とどめてみたいという願いなのです。カメラのシャッターが切り取る瞬間。絵筆のひと刷きが描く光沢。あなたのあのつややかな記憶。すべて≪微分≫です。人間のはかない“祈り”のようなものですね。≪微分≫によって、そこにとどめられたものは、凍結された時間ではなく、それがふたたび動きだそうとする、その効果なのです。 』
『 フェルメールの絵の中の光が、あるいは影が、絵としては止まっているにもかかわらず、動いているように見える。つまり、フェルメールの絵には、そこに至るまでの時間と、そこから始まる次の時間への流れが表現されているように思える。 』
そして、福岡ハカセは「真珠の耳飾りの少女」のまなざしに魅入られます。
『 意外なほど小ぶりな絵の中から、彼女はまっすぐに私を見ている。いや正確にはそうではない。それは彼女の目を見返してみると気づく。まったく曇りのない、虹彩の大きさまでわかるようなその澄んだ瞳は、私の身体を素通りして私の背後の、もっと遠くの場所に投げかけられている。彼女の前で、私は透明な存在にすぎない。薄い眉と細い鼻筋。それとはまったく対照的な、艶やかに濡れた赤い唇。無垢でありながら、ひそやかな情念を秘めた、真珠の耳飾りの少女。 』
福岡ハカセほど的確な表現はできませんが、私もこの絵には、いわく名状しがたい蠱惑的(こわくてき)な何かを感じます。それは、この絵を目にする都度脳裏をよぎる、あの歌のせいかもしれません。
「白玉か何ぞと人の問ひし時 つゆとこたへて消えなましものを 」
この歌と「真珠の耳飾りの少女」とは、私の中で分かちがたく結びついています。
この歌は、伊勢物語の第六段、通称「芥川」の歌です。伊勢物語は「むかし、男ありけり」で始まる平安初期の歌物語。そして、この「芥川」は、伊勢物語の中でもとりわけ有名なくだりで、教科書にもよく掲載されています。300文字にも満たない非常にコンパクトな内容なので、全文を引用します。
『むかし、男ありけり。女のえ得まじかりるを、年を経てよばひわたりけるを、からうして盗みいでて、いと暗きに来けり。芥川といふ川を率て行きければ、草の上に置きたりける露を、「かれはなにぞ」となむ男に問ひける。行く先多く、夜もふけにければ、鬼ある所とも知らで、神さへいといみじう鳴り、雨もいたう降りければ、あばらなる蔵に、女をば奥におし入れて、男、弓、胡籙を負ひて戸口にをり。はや夜も明けなむと思ひつつゐたりけるに、鬼はや一口に食ひてけり。「あなや」と言ひけれど、神鳴るさわぎに、え聞かざりけり。やうやう夜も明けゆくに、見れば率て来し女もなし。足ずりをして泣けども、かひなし。
白玉か何ぞと人の問ひし時 つゆとこたへて消えなましものを』
大意はざっくりこんな感じです。
昔、男がいた。男は長年ある女性に求愛していたが、ついぞ叶わず。その女性を強奪することにした。女性を背負い、暗闇を逃げ急ぐ中、ある川のほとりにさしかかる。川辺の草の葉には無数の露が。露は月影を浴びて光り輝いていた。女性は問うた。「あれは何ですか。」と。
しかし、先行きはまだ遠い。夜も更けてきた。折しも、雷鳴轟然(らいめいごぜん)、沛雨騒然(はいうそうぜん)と。男は黙然として先を急いだ。そして道中、ボロボロの蔵を見つけた。男はその蔵に女性を押し込め、武装して戸口を守ることにした。男が早く夜が明ければいいのに、と思った刹那、蔵の中に潜んでいた鬼が一口で女性を食ってしまった。「ああ」と声をあげるも、雷鳴にかき消され声は届かず。次第に夜が白んできたので、男は蔵の中をのぞいてみた。しかし、そこに女性の影はなく。男は地団駄を踏んで泣いた。だが、もう何もかも遅かった。
「あれは真珠ですか、何ですか」とあなたが聞いたとき、「あれは露だよ」と答えて、私が露と消えてしまえばよかった。
この女性は高貴な身分の姫君だったのでしょう。長年の求愛が実を結ばなかったのは、おそらく身分の違いによるものだと思います。やんごとなき姫君に懸想する道ならぬ恋。その恋路の果ては、駆け落ちならぬ強奪、略取でした。女性を背負ってえっちらおっちらと逃げる姿は、逃避行というにはあまりに喜劇的です。このとき、男の背に揺られつつ姫の胸中に去来したのはどんな思いだったのでしょうか。「あなたは私をどこへ連れていこうというの?そこに何があるの?これから私はどうなるの?どうやって暮らしていくの?父さまや母さまには何て伝えればいいの?」なぜか、彼女はひとことも発しません。
ただ、彼女は川べりにまたたく幾千、幾万の「光のつぶだち」を見て息を飲みます。魑魅魍魎(ちみもうりょう)が息を潜めつ跋扈(ばっこ)する仮初めの静寂。漆黒の闇にただただ白く輝る月は、狂気にも似た不安を駆り立てます。にもかかわらず、玉露は月影を封じて、まるでそれ自体が発光しているかのように明滅し、無数の「光のつぶだち」となって彼女をとりまく世界に突如現前します。ただ、宮廷内で、花よ蝶よと大切に育てられたやんごとなき姫君には、それが露であることがわかりません。このとき、ただひとことだけ問を投げかけます。「あれは真珠ですか、何ですか」。
姫君は、本当のところ、誰に、何を問いたかったのでしょうか?世間知らずのお嬢様の無邪気な好奇心が、「あれは真珠ですか、何ですか」と問うたのでしょうか?
思うに、彼女は生まれて初めて、外の世界へ踏み出しました。否、正確にいえば、意図せず投げ出されたのです。そこで彼女がまのあたりにしたものは、世界そのものと、その内にある存在者としての「私」。さらなる想像が赦されるなら「死」。暗示された「私の死」そのものです(そして、物語はその暗示をのちに批准します)。「光のつぶだち」は、圧倒的な「存在性」を伴って現前し、純粋体験とでもいうべき強烈な体験を彼女に科します。この純粋体験の声ならぬ声が、「あれは真珠ですか、何ですか」なのだと思うのです。
彼女が真珠に仮託した問い。それは、「そもそも存在とは何か」という「存在」そのものへの問いでした。「存在」そのものの自明性を前提にして、「世界はいかなる存在で満ちているのか」、その「いかなる」を問うたのではありません(そして、おそらくこうした問いは彼女が宮中にいるときから考え続けてきたのでしょう)。そうではなく、存在の存在性自体を問う。この問いの立て方は、ハイデガーが試みた「存在論的優位」という立論に他なりません。奇しくも彼女は存在論の深淵、哲学の蘊奥(うんおう)を、その瞬間、のぞき見てしまったのでした。
しかし、姫君の存在論的転回も虚しく、男は黙殺を以ってその契機を剥奪してしまいます。夜陰、雷鳴、沛雨、魑魅魍魎(そして、これらはすべて、死を暗示します)から姫君を守りたい。その一心で。そして、姫を蔵に引き入れ、戸口を守るのですが、敵は内にあり。哀れ、姫君は鬼に一口で食われてしまいます。
男の身勝手さ、愚かしさは、今さら言うまでもありません。古今を問わず普遍。泣けど詮なし、嘆けど甲斐なし。ただ、男が最も後悔したのは、姫君の存在論的転回の契機を剥奪したこと。これは姫君自身を宮中から略取した「身体性の掠奪」よりも罪深いことです。そして更に罪深いことに、男は姫の問いが真に意味するところを、実は気づいていました。あのとき「あれは露だよ」とひとこと答えてあげていれば、たとえ鬼に食われて短い生涯を閉じる運命にあったとしても、彼女の生まれいずる理由(存在とは何かという問い)は成就されたであろうに。その唯一の契機を、半ば意識しつつ剥奪してしまったのでした。
その懺悔、贖罪の祈りが、
「あれは真珠ですか、何ですか」とあなたが聞いたとき、「あれは露だよ」と答えて、私が露と消えてしまえばよかった。
という歌に込められています。ただ、お前が掠奪しなきゃ、そもそもこんなことにはならなかっただろうに、の一言で終わる話でもあるので、やっぱり男は身勝手で、愚かですね。
冒頭のフェルメール作「真珠の耳飾りの少女」ですが、私の中では芥川の鬼に食われた姫君とわかちがたく結びついています。男の背で「あれは真珠ですか、何ですか」と問うた彼女は、おそらくこんな表情をしていたのだと思います。
これは、真珠からの連想だけではありません。『私の身体を素通りして私の背後の、もっと遠くの場所に投げかけられている』不思議な視線。彼女の視線の先に「私」はなく、かといって、彼女が見つめているのは虚空でもありません。彼女のまなざしのその先は、「いま、ここ」のはるかなる先、どこかにあるであろう存在論的な彼岸だったに違いありません。
そして、「あれは真珠ですか、何ですか」という問いかけが、世界を微分します。その刹那、そこに至るまでの時間と、そこから始まる次の時間への流れは、彼女の視線の先にある一点で交叉し、世界は凝縮された「光のつぶだち」として静止します。これは一瞬の生死の明滅、存在論のまたたきのようなもの。そして次の刹那、世界はふたたび動き出すのです。
一点の絵画、一首の詩歌、300文字に満たない物語。これらの一隅に触れたに過ぎませんが、アートや古典が持っている象徴表現の豊穣さに改めて驚愕するとともに、畏敬の念を禁じ得ません。
翻って、私の日常はというと・・・相も変わらず、陰影なき平板なチャートと詩想なき散文の山。この山を粗製濫造し、大量消費する毎日です。という傍から、またひとつ、粗製してしまったわけですが・・・